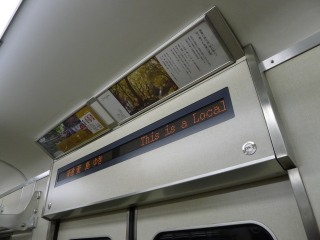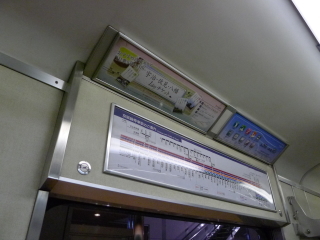| 京阪電鉄 5000系 | ||
 |
言わずと知れた日本初にして日本最後の5ドア車です。多扉車が必要だった背景や沿革については語れば長くなりそうですが、特急車と同じくらい注目を浴びていた車両ということは京阪側も承知していたようで、2023年春、くずはモールの中にあるSANZEN-HIROBAにて5000系に関する展示が始まるとのことで…座席昇降装置は?どこまで原型に復元しているのかなぁ?などなど、3000系であれだけ気合を入れた復元がみられただけに、今回もかなり期待しているところです。 今回は7両固定編成の車内の模様を中心に、2013年、2018年に取材した晩年の姿をお届けします。特に座席モケットの変更は登場時から何回変わっているの?!とツッコミを入れたくなる有様ですが、恐らく最も多くの方の記憶に残っている姿ではないかと思います。 でも…この形式に関していえば、旧塗装の方が好きです。 (取材・撮影 京阪電鉄中之島線・中之島 他) |